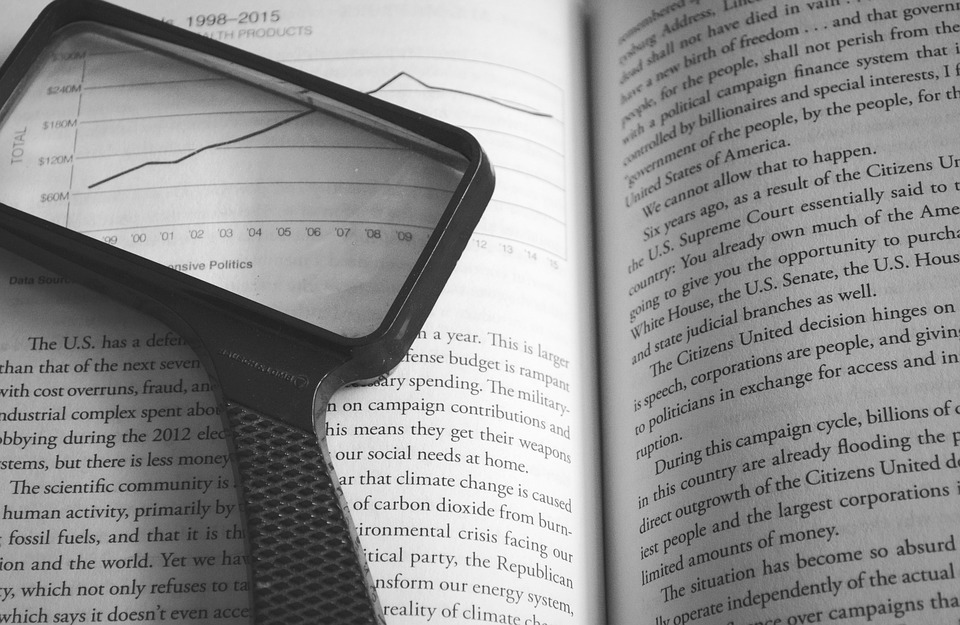Web集客の専門家、俵谷 龍佑(@tawarayaryusuke)です。
ライターという職業柄、自分が発信する情報への信頼性はかなり神経質になります。
それは、ツイッターなどのSNSにつぶやくものもそう。
もちろん、ライターにとって文章力も大切なのですが、この正しい情報かどうか見極める裏取りは本当に大切。
今日は、僕が実際に仕事で使っている情報の真偽を見抜く方法をご紹介。全部で5つ。
情報の裏取りに有効な5つの方法
1.逆行して1次情報まで辿る
Webライターの業界でも、今となっては基本中の基本のことだと思います。
昨年「Welq」の大炎上事件が発生したため、多くの企業は情報の信頼性にシビアになっています。
もちろん、企業担当者に情報の真偽を確認する時間はないのは現状で、結局、ライターの目に委ねられることになります。
そのため、この力をつけることはライターにとっての価値になります。
1次情報が国家機関、マーケティング調査会社のレポートにたどり着けばOK、1次情報がまとめサイトなら真偽の程は怪しいです。
2.一般論か、個人的意見か区別して考える
きわどい内容でも、一般論だとOKなことがあります。
Welq炎上の問題以降、特に薬事法にはうるさくなりましたが、例えば、「生姜を飲むと身体がポカポカするから、冬におすすめ」というのは、僕はOKかと思います。
というのも、これは一般論としてみんなが知っていることだから。
しかし、「生姜がデトックス効果があり、癌に効きます」と謳ったら、真っ黒にNGです。
ですので、もし際どい情報があったら、「一般論」か「個人的意見」かどうか区別して考えるようにしましょう。
3.コピペチェックツールを使う
コピペチェックツールとは、記事執筆の発注者向けに開発されたコピペ防止ツールのこと。
回数に制限はあるものの、無料で使えるものがいくつかリリースされています。
有名なところだと、「こぴらん」「Copy Content Detector」「CopyDetect」あたりです。
僕もお世話になっています。
普通、発注した記事のチェックで使いますが、僕はこれを情報があっているかどうか、どこの情報を参考にしているのかを見抜く時に使います。
というのも、

コピペチェックツールだと、このように整合率などを見ることが出来るから。
整合率が低いほど、オリジナルのものということが分かります。
(このブログ記事をツールで分析したもの。)
俵谷 龍佑
最新記事 by 俵谷 龍佑 (全て見る)
- フリーランスは「地雷案件」や「炎上案件」と、どう向き合うべきか? - 2024年5月3日
- 紹介だけで仕事が回る人がハマる落とし穴とは? - 2024年4月27日
- ミスをした人は能力不足?それともルールの欠陥にハマった犠牲者なのか? - 2024年4月18日
- ビジネス書では教えてくれない、フリーランスがあまり直視したくない現実を言語化してみた - 2024年1月17日