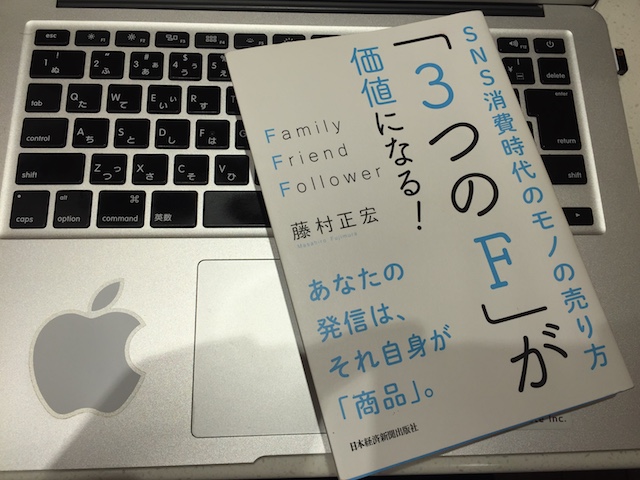俵谷龍佑(たわらやりゅうすけ)(@tawarayaryusuke)です。
SNSの使い方に悩んでいて、改めて最新のSNS活用法について学びたいと思っていたので、このたび「3つのFが価値になる」を買いました。
最近、本読んでいなかったので、ちょっと読了までに時間がかかってしまったよ。
当たり前のことばかりだけど、なかなか事例も多く骨太で読み応えありました。
いくつかポイントをピックアップしてご紹介。
SNSによって、消費の順番が逆になっている
SNSに投稿するネタがないから、面白いお店に食べに行く、話題のお店に並んで入店する、確かに言われてみれば、、という感じです。
お店のあのご飯を食べたくて!というよりは、「インスタで見たあのスイーツ私も撮ってみたい!」という動機で入店する人は確かに多そうです。
また、「3つのFが価値になる」では、このようにも書いています。
消費が企業のコントロール下から離れてしまったということ。企業側から消費者をコントールして流行を作るとか、ヒット商品をつくりなんていうことが、かなり難しい時代になったということです。
SNSによって起こるヒットが偶発的になり、企業側では狙い撃ちできなくなってきているということ。
これは裏を返せば、今までマス広告を打てなかった中小企業にも平等にチャンスが回ってきたということになります。
SNSでの振る舞いが評価の対象になる
本書でも紹介していますが、「OWNDAYS」という会社が「フォロワー1500人以上は採用を優遇」という新しい採用の方法を行っています。
これは僕は画期的だと思っています。その理由が・・・
- SNSをある程度使いこなせていなければ、1500人のフォロワーはつかない
- 面接で取り繕っても、SNSで本音が見える
- 価値観や考え方がSNSから判別できる
たとえ、フォロワーを購入していたとしても、まず「購入する」時点でSNSを使いこなせているわけで。
採用面接なんて、ほとんどが紋切り型の回答とテンプレのようなリクルートスーツなので、採用する側が見抜けるわけありません。
しかし、SNSはその人の素がどうしても出るので、どんなこと考えているのか、日頃何をしているのかというのが分かります。
今後は、採用や審査などあらゆる面で、SNSが対象になるかもしれないなと思います。
AIを使えば、SNSの投稿内容で大体分かってしまいそうだし。人の目より正確なのは間違いないですね。
論理的なことよりも、感性や非合理性が重要になる
SNS自体は、「いいね!」や「シェア」ボタンがあるように、もともと人の楽しさや喜びを共感するツールです。
人の感情には論理は介入できません。
心理学やテクニックを駆使すればある程度コントロールできますが、それを凌駕して不規則な動きをするのが感性や非合理性。
論理的に考えれば、1+1=2になるし、2+2=4になる。
つまり、みんなと同じ世界になってしまう。

過去記事でも書きましたが、再現性のない真似できない唯一無二のものを僕たちは作っていかないといけないんだと思います。
それは、存在もそうだし、仕事や事業も全部そう。
誰もできることをイヤイヤやっていても、「その分野で楽しそうにやっている人」に勝てるわけがない。
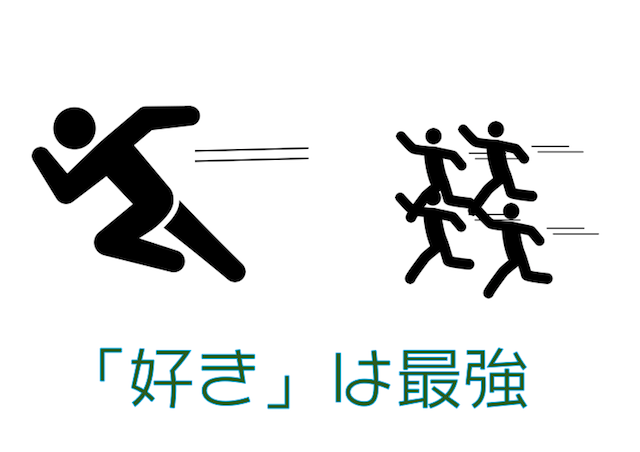
「自分だからこそできること」を探すってことと、SNSは実は関連性があるんですね。
まとめ
仕事でマーケティングをやっているので、全部ロジック(論理)で考えてしまうクセがあって、「論理よりも非合理性や感性を大切にする」という部分は非常に刺さりましたね。
ところで、自分が購入している玄米があんまり美味しくないので、知人に教えてもらった玄米を買ってみた。
届いたら商品レビューします。
今日紹介した書籍はこちら
俵谷 龍佑
最新記事 by 俵谷 龍佑 (全て見る)
- フリーランスは「地雷案件」や「炎上案件」と、どう向き合うべきか? - 2024年5月3日
- 紹介だけで仕事が回る人がハマる落とし穴とは? - 2024年4月27日
- ミスをした人は能力不足?それともルールの欠陥にハマった犠牲者なのか? - 2024年4月18日
- ビジネス書では教えてくれない、フリーランスがあまり直視したくない現実を言語化してみた - 2024年1月17日